デスクトップが死んで創作意欲が湧いたので、また懲りずに定型的なボーイミーツガールものを書いてみた。のんのんびよりの風景を見ていて、パッと思い浮かんだ情景を二日でまとめたものなので内容は荒いです。ボーイミーツガール+オチの弱いトワイライトゾーンみたいな。テレレレ テレレレ テレレレ テーテン テーテン テーテン。それは未知と空想の不思議な世界。
「じゃ、お先でーす」
「お疲れ。また明日ー」
バイト先の店長に声をかけ、帰路に着く。
十二月の寒空、薄暗い道路をとぼとぼと歩きながら、大きなため息をつく。
「はぁ…なにしてんだろう」
夢憧れて都会へ来たもののそこから進展はなく、上京してからすでに8年経った。
ミュージシャンになる夢も諦め、定職にも就かずにバイトで食いつないでいる。
バイトから帰ってきて寝て、またバイトへ行くだけのつまらない日常。
こんなはずじゃなかったのに…。
先の見えない未来とどうしようもないもどかしさで自己嫌悪に陥る。
「ただいまー」
アパートの扉を開けると誰もいない真っ暗の部屋に向かって虚しい言葉をかける。
もちろん返事はない。
バイト先でもらった弁当をレンジに入れ、コップの中のティーパックにお湯を注ぐ。
「あぁ、さみぃ」
そそくさとコタツに入り、弁当が温まるのを待っているとケータイが震えた。
「こんな時間に誰だよ」
鬱陶しそうにケータイを確認する。
母親からの電話だった。
「もしもし陽介だけど」
「陽介、久しぶり。そろそろ正月だけど今年は帰ってくるん?」
「うーん。そうだなー」
実家には三年近く帰っていない。
余計な出費をしたくないし、いまさら帰りづらいのもあった。
せめて定職にでもついていれば顔を出しやすいのだが。
だけど何年も顔を見せないのも悪い。
親だっていつまでもいるわけじゃないのだ。
「じゃあ、久しぶりに帰るわ」
「そうかい。準備しとくから。いつ来るかまた連絡して」
「うん。日付決まったら電話すっから」
「おせちも作るからね」
「はいはい」
ぶっきらぼうな返事をして電話をきる。
昔と変わらない母親の声に少し安堵している自分がいた。
人っ子一人いない駅へ降りると、懐かしい風景が目に飛び込んでくる。
このへんはほんと変わらないな。
ビルも無ければ看板もない。
老朽化の進んだ木造の家がぽつぽつと建ち並んでいる。
都会の活気とは対照的に、街は静けさに包まれ、まるで時間が止まっているようだ。
田舎にいる時はそんな風に感じなかったのに、そう感じるようになったのは自分が変わってしまったせいなのか。
乾いた風に吹かれながら変わらない風景を眺め、バスの停留所まで歩く。
「ただいまー」
実家の玄関を開け、奥の方に声をかける。
「はーい。陽介ー?」
母親の声が台所から聞こえてくる。
「うん。帰ってきたわー」
そう言いながら家へと上がる。
台所にはおせち料理の準備をしている母親がいた。
三年前とは変わりがない。
久しぶりに顔を合わせると少し気恥ずかしさを感じ、平静を装う。
「バスから歩いてきたん?もう着いてるなら車で行ったのに」
「わざわざ迎えに来てもらうのも悪いしね。まぁそんな距離もないし」
「寒かったろ。コタツ入りんね」
「うん。ありがと」
コタツに入るとテレビの横に立てかけてあるアコースティックギターが目に入った。
「これまだあったん?」
母親にギターの事を尋ねる。
「あんたの部屋掃除している時に見つけてね。父ちゃん弾かないけどたまに手入れしてるんよ」
確かによく見てみると弦は張り替えてあるし、ボディも綺麗に磨かれている。
手にとると懐かしいあの感覚が蘇る。
高校生の頃、ギタリストに憧れて、毎日練習していたあの日々を。
十年前ーーー
夕焼け空の下、ギターを背負って自転車を漕ぐ。
ギターケースが風に煽られ、じんわりと汗がにじむ。
街を見下ろせる丘に着くとギターと譜面を取り出し、いつものように練習を始めた。
誰にも邪魔されないこの場所で暗くなるまでギターを弾くのが日課だった。
お気に入りのフレーズ、もはや手癖になったリフ。
指板とにらみ合わなければ弾けなかったリフも今では目をつむっても自然に弾ける。
まずは覚えなれたリフを弾いて指慣らしをするのが決まりだった。
目をつむり、気持ち良く弾いていると突然、現実に連れ戻された。
「うまいね」
いきなり声をかけられ、心臓が止まりそうになる。
目を開くと同じ年齢くらいの女の子がこちらを見て微笑んでいた。
「えっと・・・」
見たことない子だ。
突然のことで言葉が思うように出てこない。
「ギターうまいね。わたし本物のギターはじめてみた。CDが鳴ってるみたい」
彼女は素直に感動しているようだった。
「いや、そうでもないよ」
ぼくは戸惑いながらごまかした。
「他に弾ける?聞きたい」
そう言いながら彼女は近くにそっと座る。
「ポップスはわからないけどね」
ぼくは逃げ出すタイミングを見失い、腹をくくる覚悟で弾き始めた。
カントリー、ホンキートンク、ブルース。
弾き慣れたリフを途切れないように繋げる。
手のひらから音がこぼれないように丁寧に。
「あっ、それ聞いたことある!」
彼女が嬉しそうに言う。
「コマーシャルでよく使われたりするね」
「すごいね。今の曲、もっと弾ける?」
彼女の望み通り、イントロからサビまで弾いてみせる。
「わー、かっこいいなー」
彼女の喜ぶ姿にぼくも嬉しくなった。
公民館のスピーカーから夕方のチャイムが鳴る。
「いけない。配達の途中だったんだ」
彼女はそう言うと近くに停めてある自転車の方へ走り出す。
途中で立ち止まり、こちらを振り向いた。
両手を後ろで組み、こちらへ話しかけてくる。
「きみ、名前は?わたしは三上幸子」
「吉岡陽介。南高だよ」
「陽介くん!南高校なんだー。ここでよくギター弾くの?」
「最近はそうだね。アコギはうるさくて家で弾けないから」
「そうなんだー。また来ていい?」
「う、うん・・・。ここで練習してるから」
「やったー。じゃあまたあしたね。陽介くん!」
「うん。また」
三上さんは軽く手を振ると自転車に乗り、隣町の方角へと行った。
彼女の姿が見えなくなるまで見送る。
その日は練習に身が入らず、早々に切り上げて家へ帰った。
それから学校が終わってからあの丘で三上さんと会う機会は増えていった。
三上さんが知っているようなポップスを家で練習し、ぼくの演奏に合わせて彼女が歌う。
お互いのことはほとんど知らない。二人だけの秘密のセッション。
ぼくは今まで以上にギターと真剣に向き合うようになり、四六時中ギターのことを考え、無意識に右手をストロークすることもあった。
新しい曲を覚えては三上さんに披露する。
ただそれだけで楽しかった。
「わたしもギター練習したら陽介くんみたいに弾けるかな?」
真剣な表情で三上さんが尋ねてくる。
「練習したらきっと弾けるよ。すぐには無理かもしれないけど継続すればいつかきっと。なんでもそう。学校の勉強だって、スポーツだって、いきなり初めからうまくはできないけどやり続けてたらある程度できるようになるように」
ギターを始めた頃の自分へ言い聞かせるように三上さんへ返答する。
「ほんと!それぐらい弾けたらきっと楽しいだろうなぁ。陽介くんのそのギターはいくらくらいするものなの?」
「十万弱くらいかな。お年玉を貯めて買ったんだ」
「やっぱりギターって高いんだねー」
「ピンきりだよ。 手頃なやつもあるから。値段が高いものがいいわけじゃないんだよ。ギターって」
「そういうものなの?」
三上さんは不思議そうな表情をする。
「なんて言ったらいいのかなぁ。百円のボールペンと一万円のボールペン?五千円の服と五万円のブランド服?安物は確かに作りも荒いものもあるけど、一定のラインからは好みの問題だと思う」
「でも陽介くんのギターがやっぱりかっこいいね」
「ギターって同じような見た目だけど性格が全然違ったりするからね。楽器屋さんで見るのが一番いいよ」
「陽介くんはさ、進路のこと考えてる?」
「まだあんまり考えてないかなぁ。三上さんは?」
「わたしも。でも陽介くんはギターあるじゃん」
「これでご飯食べるのは無理だと思うよ。無理、無理」
「そんなことないよ。陽介くんならきっとプロになれるよ」
「いやー・・・」
「絶対なれるって!」
そんな日が二ヶ月ほど続いただろうか。
ある日を境にパッタリと三上さんは来なくなった。
今日は家の用事が忙しいのかもしれない。
そんな風にごまかしながら毎日、あの丘へ通ったがあれ以来来ることはなかった。
なにか嫌われるようなことでも言っただろうか。
彼女を傷付けるようなことをしただろうか。
明確な理由がぼくには思い浮かばなかった。
懐かしいギターを目にし、三上さんのことを鮮明に思い出した。
短い期間だったが彼女との出来事は未だに脳裏に焼き付いて離れない。
「母さん、このギター借りていい?」
「いいもなにもあんたのギターでしょ。父ちゃん弾かんし、別にええよ」
「じゃあ出かけてくる」
「夕飯までには帰ってこんね」
「わかった」
ぼくはギターを手に取るとあの丘へ向かった。
丘から見る風景も変わらず、 あの頃のままだった。
ぼくは岩に腰掛け、ギターを弾き始めた。
目をつむり、手癖のリフを。
「やっぱりうまいね」
どこかで聞いた声に、ぼくはハッとして目を開けた。
そこには昔と変わらない三上さんが立っていた。
「陽介くん、久しぶり」
「み、三上さん・・・」
突然の再開にびっくりして声も出ない。
「なに驚いてるの?前みたいにさ、ギター弾いてみてよ」
「う、うん」
困惑しながらぼくはギターを弾き始めた。
三上さんの知ってるポップス、お気に入りの曲を。
それに合わせて彼女は歌い出す。
弾いているうちに気持ちよくなり、再び目をつむり、メロディを紡ぐ。
しばらくすると彼女の声が止んだ。
ふと目を開けると彼女の姿はなかった。
周りを見渡してもここにいるのは自分だけ。
「三上さん?三上さん!」
声が虚しく響き、冷たい風がビューと吹く。
狐につままれたような出来事に呆然とするしかなかった。
どれくらい経っただろう。
ぼくは無意識のうちに家へと帰っていた。
「あら陽介、早かったんね」
「母さん。このへんに三上って家あるん?」
「三上ねぇ・・・?もしかして隣町のカミヤス酒屋さんとこじゃない?でも、あんた酒飲まんでしょ」
「うん。またちょっと家出てくるわ」
ぼくはギターをスタンドに立てかけると慌てて家を飛び出した。
母親のママチャリに乗り、隣町を目指す。
ここからなら十分もかからない。
道行く人に酒屋の場所を訪ね、ようやく到着した。
カミヤス酒屋は小さな佇まいだった。
半ば趣味のような感じで営んでいるのだろう。
扉をスライドさせ、中へと入る。
中には誰もいない。
「すいません。誰かいませんかー?」
すると奥の方から年配の女性が出てきた。
「はいー、いらっしゃい。あら、よその方?」
多分、三上さんの母親だろう。目元のあたりがそっくりだ。
ぼくは頭を振り絞り、出任せで取り繕う。
「あのー、ぼく吉岡といいます。三上さんと中学の時に一緒で。 今度、同窓会するんで連絡に来たんですよ」
「あら~、そうですか。あの子の・・・」
おばさんは虚空を見つめ、少し考え込むとゆっくりと話し始めた。
「あの子、七年前に死んだんですよ。交通事故で」
「えっ・・・」
予想外の答えに唖然とするしかなかった。
「そうだ。よかったら挨拶してやってくださいよ。あの子、きっと喜びますから」
おばさんは後ろの戸を開ける。
「はい・・・」
そう答えるしかなかった。
仏壇に飾られた写真立てには笑顔の三上さんがいた。
今でも生きているようで実感が湧かない。
ぼくは仏壇の前に座ると手を合わせて目をつむる。
そもそもさっきあの丘で出会った彼女は一体なんだったのか。
ぼくの頭は疑問でいっぱいで冷静に考えることなどできなかった。
仏壇の隣には見覚えのあるギターが立てかけてあった。
エー・ワイリのスタンダード。
ぼくが初めて買ったギターと同じモデルだ。
「このギターは?」
ぼくはおばさんに尋ねる。
「これは生前、あの子が欲しがっていたギターで。今までねだったりするような子じゃなかったんですけど、このギターが欲しいって突然言い出しましてね。親としては嬉しかったんですよ。趣味のない子でしたから。二ヶ月、毎日配達手伝ったら買ってあげるよって約束してたんですけど、その前に交通事故に巻き込まれてね」
長年、もつれていた疑問がついにほどけた。
「そうでしたか。すいません。失礼なこと聞いて」
「いえいえ。お友達が来てくれて、あの子も喜んでますよ。よかったらまた来てあげて下さい」
「はい。今日はありがとうございました」
ぼくは放心状態のまま、いつの間にか家へと着いていた。
「どこ行ってたの?」
母親が尋ねているのが耳に入ったが、言葉にならない返事しかできなかった。
自分の部屋へと入り、ベッドに横になる。
目をつむり、手癖のリフを思い出す。
頭の中に指板が広がり、思い浮かんだメロディを反芻する。
すると暗闇の中に笑顔の三上さんがぼやっと浮かび上がり、こういった。
「陽介くんならきっとプロになれるよ」



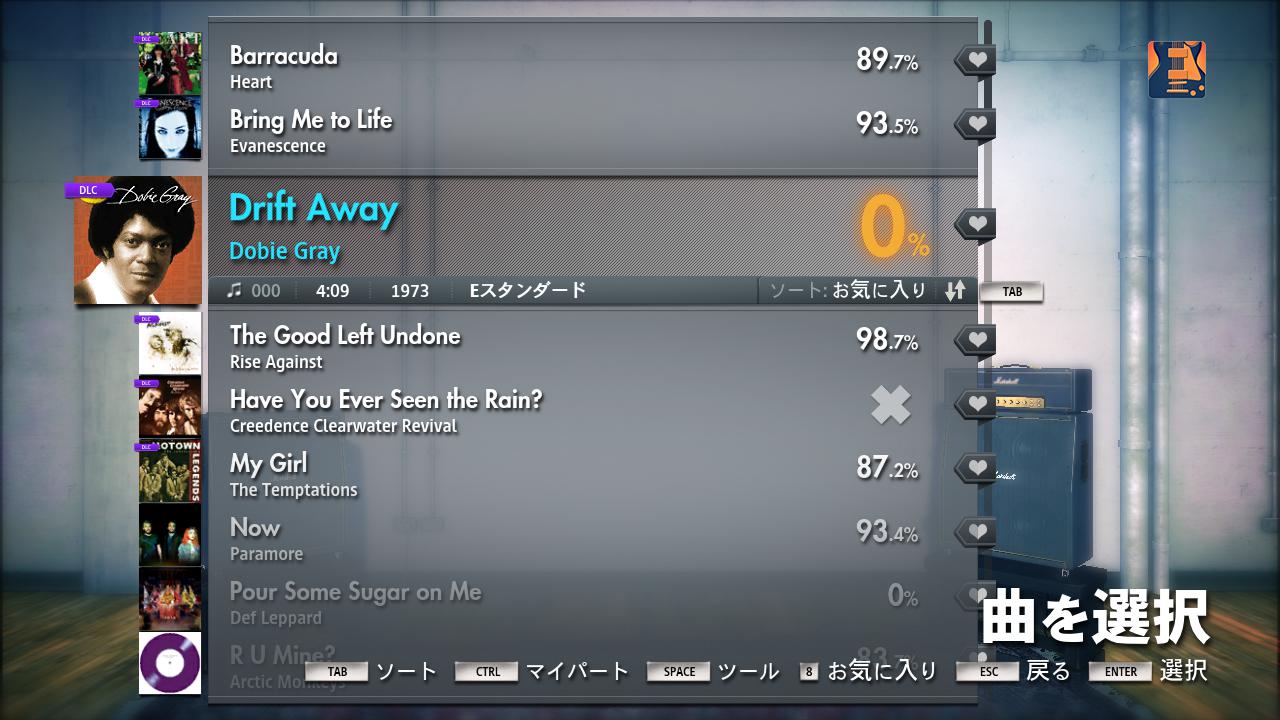
コメント
湧いたのは性欲じゃないんですか(正論)
さらりと読めて素直に感動しました。文才ありますねー。うらやましいです。
三点リーダを使いましょう……。あと感嘆符と疑問符の後ろにスペースを置きましょう! 約物は守って損じゃないです。
こういうのは 求めてないです。
痛い
でもそういう反応求めてんだろ?
性欲も創作意欲も最終的には体の中のものを出すので似たようなものだから(正論)
>>yuukiさん
ジュブナイルものっぽく読みやすい平易な文章を意識して書いたのでさらっと読めたのなら幸いです。
三点リーダは変換するのが面倒でその時の勢いで使ったり使わなかったりするので今度からは意識しようと思いました(粉蜜柑)
ジュブナイルは痛いものだからね。仕方ないね。
今度は腹の中で飼っていたドジョウが総理大臣になる話をブチ込んでやるぞオイ!
「UnKnownくんならきっとプロ(作家)になれるよ」
こんなのでなれたらプロいらないんだよなぁ(現実派)