ギターのあるあるネタが詰まったエッセイ的な読み物をいつか書いてみたいなぁと思っていたんですが、White Album 2を見ていて、ギターのチュートリアル的要素を含んだ学園もののギタリスト成長物語もいいかなぁと考え、木曜日ぐらいから寝る前にipadでメモ書きを始めたものです。ギターのテクニックや周辺機器の解説、ギターという趣味ができた主人公の変化、部活を通しての新たなコミュニティの形成、彼女と彼女の兄(ギター講師)の関係の修復を経て、たった3ヶ月で学園祭デビューという大枠は考えたんですが、でも自分にはこういうジュブナイル的な話を書くのは気恥ずかしくて、合わないなぁと実感。妄想垂れ流しのラノベとかクスリでもやらないと発表できないですよね。iCloudのメモが便利なのに気付いたのは大きな収穫でした。まぁそんなに文章書くことないですけど。あと久しぶりにハロウィン聞きました。
1st GIG – Smells Like Teen Spirit
ぼくは通学電車に揺られながら扉にもたれて窓の外の風景を眺めていた。
「次は最橋ー。最橋ー」
次の駅を知らせるアナウンスが聞こえてくる。
電車が緩やかに停止し、反対側の扉が開く。
数人入ってくるのが窓の反射で見えた。
降りる駅まではあと二駅。十五分ってところだな。
鞄からイヤホンを取り出し、音楽プレイヤーの電源を入れた。
周りの雑音が聞こえないようにボリュームを大きめに設定する。
爆音が頭に鳴り響き、周りの音が一切聞こえなくなる。
頭の中に人で埋め尽くされたライブ会場が広がった。
ステージの一番前に立って激しいシャウトを繰り返しながら泣き叫ぶようなギターを弾き、客を煽る。
ぼくの合図で観客は大合唱を始めた。右手の拳を強く握りしめ、さらに観客を煽る。
盛り上がりが最高潮に達し、ギターソロへと入ろうとした瞬間、急に甘い匂いがぼくの鼻腔をくすぐり、ロックの世界から現実へ連れ戻された。
ふと車内に目を移すと同じ高校の制服を着た女の子が俯きながら隣のポールにもたれている。
彼女は綺麗な黒髪で身長はぼくと同じくらい、いや少し高いかもしれない。
目が少しキツめだが顔立ちは整っている。
そういえば見た覚えがある。同じ学年の子だったかな。
名前は知らないが綺麗な子だったから印象に残っている。
まじまじと見ていたのに気付いたのか、彼女は顔を上げ、こちらを向いた。
ぼくはあわてて窓の外に目を逸らし、誤魔化すように音楽プレイヤーのボタンをいじる。
動揺を隠すためにさらにボリュームを上げた。
彼女はきっとぼくが見ていたのに気付いたのだろう。
じろじろと見られて、気持ち悪いとでも思っているかもしれい。
普通はそう思うもんだよな。男のぼくでさえそう思う。
彼女を意識し始めると急に息ができなくなってくる。
ダメだ。ここで息を荒げたら余計に変なやつだと誤解されてしまう。
一度、息を止めて、ほんの少しだけ呼吸する。
く、くるしい…。
まともに息ができなくて頭がぼーっとしてくる。
そこへ救いのアナウンスが届いた。
「次は田神ー。田神ー」
電車が止まると我先にと下車した。彼女の方を見ないようにしながら。
怖くて見ることはできなかった。
ホームから少し離れたところで肩で大きく息をする。
呼吸が整っててくると冷静さを取り戻した。
そしてぼくは重大なことに気付いた。
「降りるの次の駅だ…」
2nd GIG – Eagle Fly Free
罰の悪そうな表情を作ってから、教室の扉を開けた。
教室中の視線が一斉にこちらに集まる。
「遅れてすいません」
蚊の鳴くような声で謝りながらそそくさと自分の席へとついた。
「どうした?また寝坊か」
英語の教師がぶっきらぼうに尋ねてくる。
「朝からお腹の調子が悪くて、それで…」
とっさに嘘をつく。
正直に理由を話して教師やクラスメイトにバカにされたくなかった。
それに説明するのもわずらわしかったのだ。
鞄から教科書と筆記用具を取り出し、ノートを取るふりをする。
教師が喋っているが頭になにも入ってこない。
さっきからぼくの頭の中は朝に嗅いだ彼女の匂いでいっぱいだった。
休み時間は机に突っ伏して寝て、昼休みは弁当を半分食べて、また寝る。
クラスメイトと積極的に話す話題もない。
夜中までゲームやラジオを聞いて夜更かししていたせいで本当に眠かったのだ。
その日は無気力なまま下校時間が訪れた。
「それでは今日のホームルーム終わり。寄り道しないで気をつけて帰れよ」
担任がいつもの挨拶をして、教室から出て行った。
教科書を鞄につめて、帰る準備をする。
どうせ教科書なんて持って帰っても勉強なんてしないが空っぽの鞄で帰るのはなぜかいやだった。
突然、勢いよく教室の扉が開いた。
クラスメイトは驚いた様子で扉の方を見る。
扉の前にいたのはあの彼女だった。
彼女は教室を見回し、朝と同じように目が合った。
ぼくはあの時のように目線を逸らす。
そして教科書を鞄につめるふりを始めた。
彼女が近付いてきて、ぼくの机の前で立ち止まる。
「ちょっと一緒に来てほしいんだけど」
予想外の彼女の言葉にぼくは思わず固まってしまう。
「えっ、え?なんで?」
言葉に詰まりながら精一杯の返答をする。
すると彼女は表情を変えず、感情の読み取れない声でもう一度誘ってきた。
「時間あるでしょ?すこしだけでいいから」
彼女の言葉に図星を突かれて、少し腹が立ったが事実だ。
高校生になってから部活は入らなかったし、 熱中できるようなものもなにもなかった。
家へ帰っても本を読んで、ラジオを聞いて、ゲームしかすることはない。
それでもなお固まっていたぼくに対して、彼女は再び声をかける。
「先生が用があるんだって。手伝ってほしいことがあるって」
その言葉に少し落胆しながら椅子から立ち上がった。
「わかった。いこう」
周りのクラスメイトも事情を察したようでいつもの雰囲気へと戻っていた。
少し距離を取りながら彼女のあとを付いて行く。
並んで歩く勇気はなかった。声をかける勇気もなかった。
どうせあとになったらすべて分かることだ。
第二音楽室の前へ行くと彼女はポケットから鍵を取り出し、手慣れた様子で扉を開けた。
「入って、どうぞ」
彼女はぼくの方を少し振り向き、中へ入っていく。
ぼくもあとに続いて中へ入ると扉を閉めた。
当たり前だが中には誰もいない。
先生はあとから来るのかな。
「じゃあ、そこに座って」
彼女は出したままにしてあった椅子へ座るように促してくる。
ぼくは言われた通りに椅子へと腰掛けた。
彼女は部屋に置かれていたギターケースを開け、中からギターを取り出した。
ボディのふちが黒色で、はっきり木目が出たオレンジ色のギター。
ギターをこんなに近くで見るのははじめてかもしれない。
彼女は四十センチほどの黒色のスピーカーに繋いであったケーブルの反対側をギターへ差し、スピーカーの電源をつけた。
そしてそのギターをぼくへ手渡してくる。
ぼくは従順にギターを受け取る。
思っていたよりも重く、どっしりとした存在感がある。
ボディはツルツルしていて触り心地はよかった。
彼女は三角形のピックをぼくの前へ差し出した。
「ピック、これで弾いてみて」
「えっ?」
なにを考えているのか、表情からは一切読み取れない。
ぼくは返す言葉もなく、ただ固まるしかなかった。
沈黙が続く。
ぼくはいたたまれなくなり、おずおずと返事をする。
「ギターなんて弾いたことないし・・・それに先生は?」
「弾いてみて」
彼女は真剣な眼差しでぼくを見つめている。
「だから弾いたことないって」
説明になっていない彼女の言葉に困惑し、焦った口調で拒否を示した。
「知ってる。弾いてみて」
彼女は表情を変えずに同じ言葉を繰り返した。
どう返事すればいいのか。わからなかった。
ぼくは目線を逸らし、ジーッと小さなノイズを鳴らしているスピーカーの方を見つめて黙りこむ。
気まずい時間が流れる。
「ヘロウィン、好きなんでしょ」
彼女はボソッとそう呟いた。
予期せぬ言葉にびっくりする。
彼女の口からその言葉が出てくるとは思いもしなかった。
ヘロウィン…ドラマティックで疾走感に溢れるメロディと曲名を連呼するサビが特徴のドイツのバンドだ。
そしてぼくの一番好きなバンドでもある。
彼らの曲は何千、何万回聴いても聴き飽きない。
だけどヘロウィンを知っているやつは一人もいない。
ゼッペリンも、ジープディープルも、ラインボウも、スカーリオンズも。
周りのやつらはテレビから流れてくるポップスしか知らない。
まともなロックを聴いたことがないようなやつらばかりだ。
彼女の思いがけぬ言葉にぼくは少し興奮しながら聞き返した。
「へ、ヘロウィン知ってるの?」
「アルバムぜんぶ持ってる。初期が一番いい」
同意見だ。初期のヘロウィンは演奏や歌は荒々しいし、ノイズ混じりだが勢いがあって好きだ。
彼女がヘロウィンをまさか知ってるなんて。軽い驚きと共に彼女を見る目が変わった。
だけどぼくがヘロウィンを好きなことをなぜ知っているのか。
新たな疑問が浮かんだ。
彼女はそれ以上なにも言わず、黙ってぼくの方を見ている。
「わかったよ」
ぼくはその状況にとうとう耐えきれなくなり、ピックを受け取ろうとする。
ピックを受け取った時に彼女の手に触れ、少しドキッとした。
受け取った三角形のピックは想像よりも薄っぺらく、弾力性がある。
ピックを右手の親指と人差し指の腹で軽くつまんだ。
ピックなんて握ったことがない。
ライブの映像はたくさん見てきたがピックの握り方なんて意識したことがなかった。
彼女はポケットからピックをもう一つ取り出すと親指と人差し指で握る。
「こう握るの。人差し指を折り曲げて。その上にピックを置いて、親指で落ちないように押さえる」
見よう見まねで彼女と同じようにピックを握る。
つまむよりもこっちの方が安定する。
彼女はスピーカーのボリュームを捻る。
「音出すよ」
弦に軽く指が触れていたせいでスピーカーは不揃いな情けない音を発した。
弦に触れないようにしてギターを抱え直す。
そして彼女はぼくにこう言った。
「開放弦、弾いてみて」
聞きなれない言葉に再び固まり、おそるおそる聞き返した。
「かいほーげん?」
アーティストの名前だろうか。
ロックの知識には自信はあるがそんな名前は聞いたことがなかった。
「弦を押さえないで弾くから開放弦。そのままピックですべての弦を弾いて」
かいほーげんというものが弾き方のことだと気付き、恥ずかしさを覚える。
ぼくは深呼吸してから、右手でつまんだピックで勢いよく弦を弾いた。
もうどうにでもなれ。
すると今度は太くて伸びのあるロックの音が室内に響いた。
はじめて耳にする生のギターの音に鳥肌が立つ。
この音をぼくがいま出しているなんて。
「いいね。じゃあ私とセッションしよ」
彼女は立てかけてあったケースからもう一本ギターを取り出す。
美しい白色の長いギターだ。彼女の雰囲気に合っている。
なぜか弦は四本しかない。
彼女はぼくがじっとそのギターを見ているのに気付くと説明する。
「これはベース。四弦しかないでしょ。ギターは六弦」
彼女はスピーカーのもう一つの穴にケーブルを差し込み、ベースと繋いだ。
そして親指で勢いよくベースの弦を弾き、流れるような低音を奏ではじめた。
ズッシリとした低音が身体中に響き、その華麗な演奏に呆然とする。
すごい。まるでプロみたいだ。
食い入るように彼女の演奏に見入る。
「うまいね…」
素直な感想だった。
「まだまだだよ。まだまだ」
彼女は自分へ言い聞かせるように否定する。
「わたしがベースを弾くからそれに合わせて弾いて」
そういうと彼女はベースで一定のフレーズを繰り返す。
「ワン、トゥー、スリー、フォー。ワン、トゥー、スリー、フォー。ワンとスリーで六弦開放」
「ろくげん、かいほう」
聞き慣れない言葉をまたオウム返しする。
「六弦。いちばん太い弦。いちばん上の弦。それを押さえずに弾いて」
彼女はギターの一番上の弦を指差す。
ぼくは言われた通り六弦をピックで力強く弾いた。
ギター全体が振動し、身体に伝わる。
スピーカーから低い単音が鳴った。
「そう。ワンとスリーだけ弾いて」
彼女は再びカウントを取りながら同じフレーズを繰り返す。
ぼくはそれに合わせて六弦を弾く。
なにも考えずに右手だけを動かす。
はじめはぎこちなかったタイミングもじょじょに合い、自然と右手が動き始めた。
まるで身体全体が彼女のベース音を感じ取っているように。
「そう。そういうこと。次は単音。六弦の三、四、五、六フレットを順に弾いて」
彼女はギターに埋め込まれた鉄の棒を指差す。
どうやらこの鉄の棒のことをフレットというらしい。
「いちばん上が一フレット。 三フレットに人差し指を置いて。押さえる場所はフレットの真上じゃなくて少し左」
言われた通り、左手の人差し指で三フレットを押さえる。
「三フレットを人差し指で押さえたまま、中指四フレット、薬指五フレット、小指六フレット。順番に押さえてみて」
簡単そうに言うがこれがなかなか難しい。
薬指と小指にまともに力が入らない。
「じゃあ、今度は順番に弾いて。 ゆっくりでいいから」
左手の指で押さえて、右手のピックで弾く。
同じ速度で順番に弾いてみようとするが弦をうまく押さえられない。
ピックを空振りしたり、深く入れすぎてしまう。
ギタリストが軽々とやっていることがこんなに難しいとは思いもしなかった。
一度、止まったら人差し指からやり直し、それを繰り返す。
何度か繰り返すと次第に左手と右手のタイミングが一致し、規則的に音を鳴らせるようになっていた。
「いいよ。ベース弾くからさっきと同じように合わせて」
彼女は再びベースで、あのフレーズを繰り返し、カウントする。
彼女のカウントに合わせて人差し指から順番に弦を押さえ、右手で弾く。
無意識に身体もカウントに合わせて動き始める。
いつの間にか弦を弾くことに夢中になっていた。
「いい感じだね」
彼女がふと微笑んだような気がした。
改めて彼女の顔を見ると無表情に戻っている。
彼女はスピーカーのボリュームを絞ってから電源をオフにすると、ギターケースからおもむろに紙を取り出した。
「ギター部、入るでしょ?入るよね」
疑問系から突然強めの口調に変わる。
「い、いや・・・」
反射的に否定しようとするが、彼女がさらに畳み掛ける。
「ギター部、入るよね」
そう言いながら持っていた紙を無理やりぼくへ手渡した。
入部届。
紙には大きな字でそう書いてあった。
「いや、だけどギター持ってないから」
「それ貸してあげる。使っていいから」
ぼくの言葉に被せるようにして、彼女が遮る。
彼女に逆らうのは難しいと悟ったぼくは曖昧な言葉で濁した。
「考えてみる」
「じゃあ、ギターとこれ貸してあげるから」
長方形のプラスチックからプラグが生えたようなおもちゃを渡してくる。
「これは?」
一体なんなのか分からなかった。
「小型のアンプ。これをギターに挿してヘッドフォンを挿したら音が鳴るから」
よく見るとそのおもちゃにはボリュームを調整するつまみもある。
「へぇ~」
こんなもので音が鳴るのか半信半疑だったがとりあえず受け取っておくことにした。
鞄にアンプをつめる。
ギターをケースにしまうと彼女は音楽室の鍵を取り出した。
「今日やったこと。家でちゃんと復習してね」
「うん…」
ぼくは彼女からギターケースを受け取り、右肩に担いだ。
廊下に出ると彼女は鍵を閉める。
「じゃあ」
一言そう言うと廊下を歩き始める。
「うん…」
ぼくは生返事し、彼女の後ろ姿を見送った。
廊下で呆然と立ち尽くし、今日の出来事を振り返る。
なぜこんなことになったのか。
綺麗な女の子に話しかけられて。
一緒にギターを弾いて。
部活に勧誘された。
しかも入部を断るのは難しいときた。
だが、ギターを弾いた時のあの感触、彼女のあの匂いを思い出すとそれでもいいかなと考えている自分がいた。
左手の指が少しヒリヒリする。

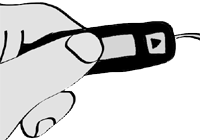
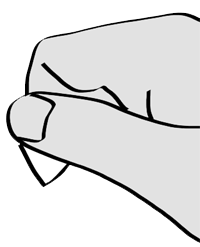
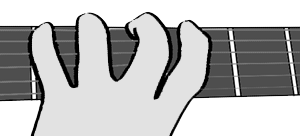
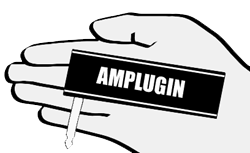
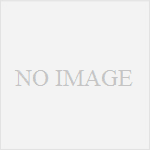
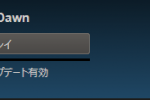
コメント
クスリやらなくても僕は書けるので執筆に参加させてくださいよ。絵は何を使って描きました?あと、ガレージバンドをやろうかなと思っています。
ZOEちゃんは、難病にかかった白痴同然の純粋無垢な女の子(金髪ロリ)が主人公と大恋愛した末に病で死ぬ純愛物語をさっさと書いて、どうぞ。
絵は自分の手を見ながらInkscapeでちゃちゃっと模写ですね。
ギターを知らない人の為に絵が必要だと思ったのですが、ライトノベルにありそうな萌え絵なんて書けないし、絵の勉強をしようとも思わないのでしょぼい絵でお茶を濁しました。
ガレージバンドはipad版から入った方が楽しいかなと思います。タッチでギターやドラム音を打ち込めるので。
前はアンプ代わりに使ってましたが、最近は触ってないですねー。ipadも動画やラジオを見ることにしか使ってない。
Unknown兄貴は小説も書けるのかぁ。たまげたなぁ(小並感)。
僕は、ラノベを書くとしたら、百合百合なガールズ・ロックバンドの学園物ラノベが書きたいです。
ギター・ベース・ドラムのスリー・ピース、全員ヴォーカルも行う。
出版前からアニメ化確定済み(予定)、メインキャラクターの声優は悠木碧と大坪由佳と藤田咲(予定)。
本のイラスト・アニメ監督・アニメキャラデザはりょーちも(予定)。
作中のオリジナル楽曲の作詞作曲編曲・ミキシング・マスタリング・音響監督は全て僕が担当(予定)。
#多分書かない(予定)。
この書き込みは黒歴史化する(確定)。
Y.AOI姉貴はミナツェペッシュやヴィクトリカ声でオナシャス。